

モンシロチョウの繁殖行動
モンシロチョウの幼虫は、キャベツなどのアブラナ科植物を食べて育ちます。十分に成長すると、蛹をへて成虫に羽化します。羽化した成虫は、その日にはあまり活動しません。特に羽化後2-3時間ほどは、葉の下でジーッとしています。殆どのメスはこの期間に、飛んできたオスと交尾します。交尾後、オスはすぐに新たなメスを求めて飛び始めますが、メスは数日間は交尾を受け入れず、産卵・吸蜜に専念します。
つまりオスは毎日でも交尾可能ですが、メスは数日に1度しか交尾しません。またモンシロチョウの成虫での平均寿命は、1週間以下です。更に、メスは1回の交尾で十分な精子を受け取るので、2度目に交尾したオスの精子が使われる割合は低くなります。そこで、羽化したてのメスをなるべく早く発見して交尾するオスほど、多くの子孫が残せることになります。
歳をとったオスほど長く探索する
 このように、モンシロチョウのオスの間には、羽化したてのメスをめぐって競争が起きていると思われます。競争の結果、最も効率的な探し方が淘汰されてきたと考えられます。私たちは、オスが実際にはどのようにメスを探しているのか、野外での行動観察を行いました。その結果、€気象条件によって探索行動が変わること、 探索行動に大きな個体差があること、¡羽化後に日がたったオスほど、長い時間探索を続けることが分かりました(右図)。今回はこの内、成虫齢と探索時間の関係について注目しました。
このように、モンシロチョウのオスの間には、羽化したてのメスをめぐって競争が起きていると思われます。競争の結果、最も効率的な探し方が淘汰されてきたと考えられます。私たちは、オスが実際にはどのようにメスを探しているのか、野外での行動観察を行いました。その結果、€気象条件によって探索行動が変わること、 探索行動に大きな個体差があること、¡羽化後に日がたったオスほど、長い時間探索を続けることが分かりました(右図)。今回はこの内、成虫齢と探索時間の関係について注目しました。
歳をとるほど長い時間メスを捜すことが、なぜ「効率的」なのでしょうか。第1に考えられる仮説は、現在と将来の繁殖のトレードオフです。つまり、オスがメスを探すために活発に飛び回ることがオスの死亡率を高めてしまう場合、若い内には無暗に飛び回らず、これから羽化してくるメスを待っていた方が得策です。ですが日がたつにつれ、新たに羽化するメスの数も減少しますし、「老化」により死亡率も高くなります。そこで、歳をとったオスはなりふり構わず探索に時間を割いてしまうのではないか、という仮説です。
 シミュレーションによる考察
シミュレーションによる考察
この仮説では、探索によってオスの死亡率が高くなる(右図)と仮定していますが、実際にはその関係は実測はされていません。ですので、探索時間と死亡率の関係がどの程度の強ければ、上のような現象が起きるのか、コンピュータによるシミュレーションを行いました(条件は以下の通り)。


その結果、探索時間と死亡率の比例定数がかなり高い(0.6以上)場合には、日齢と探索時間の相関が生じうることが分かりました(左図)。比例定数が0.5以上というのは、モンシロチョウのオスが1日中探索を行うと、50%以上の確率で死亡してしまう状態のことです。


比例定数が0.6以上という値は、実際の値に比べ多少大きすぎる可能性があります。野外ではオスとメスの寿命に大きな差は見られませんが、比例定数が0.6以上でのシミュレーションではオスがメスに比べかなり短命になってしまいます。そこで、新たに「探索に適した時間帯」という要素を加えてみました(右上図)。実際に野外では、探すの対象のメスが早朝に集中して羽化しますし、オスの探索行動も午前中の方が多いことが知られています。ですので、一定時間以上は探索を行っても、それほど発見率には貢献しないと条件で同様のシミュレーションを行いました。すると、「探索に適した時間帯」が0.5以下の場合には、探索時間と死亡率の比例定数が多少低くて(0.4)も構わないことが分かりました(右図)。
以上、いずれにせよ探索時間と死亡率に強い相関があれば、年寄りオスほど熱心にメスを探すという現象が説明可能なことが分かりました。モンシロチョウのオスの探索時の死亡原因としては、捕食・高温障害(真夏に活動しすぎて生理的な死亡率が上昇)が考えられますが、何れもまだ測定されていません。これらの要因を測定し、定量的な考察を行うことが今後の課題です。
ソフトウェア |
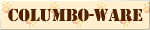 |
|---|
| Excel関連のリンク集 | 日本語入力の関連のリンク集 | 統計をやさしく解説 |
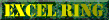 |
 |
 |
|---|
| 廣田 忠雄 @ 山形大学 理学部 生物学科 生物多様性大講座 |
|---|